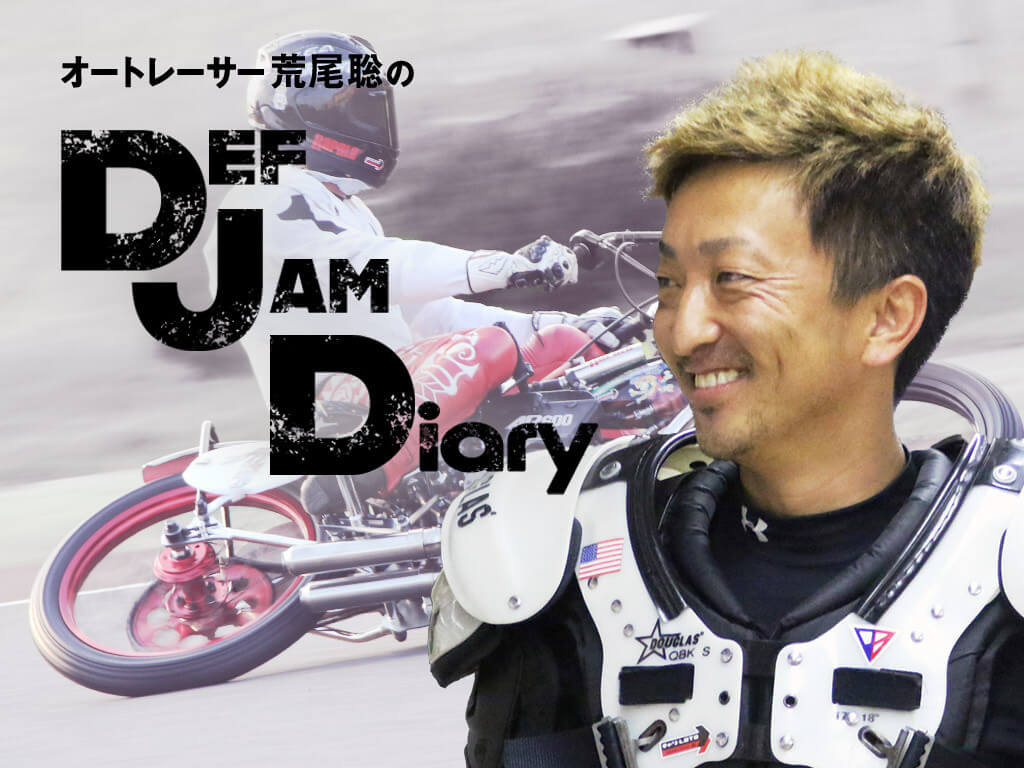ナショナルチームのアピール

2020年東京五輪に向け、日本代表に勢いがついてきた。一昨年12月、ワールドカップ第4 戦の男子ケイリン(サンティアゴ)で脇本雄太が太田真一、矢口啓一郎に続いて、日本人3人目、14年ぶりの金メダルを獲得。これを皮切りに、昨年の3月に行われた世界選手権(アペルドールン)では河端朋之が男子ケイリンで銀メダル。これだけに留まらず、昨年10月、今シーズンのワールドカップ開幕戦大会(パリ)で脇本が再び優勝。日本人として初の複数回Vを成し遂げたのだ。
脇本の金メダルは前述したように昨年が第4戦で、昨年が初戦……実は大きな違いがある。通常、各国は世界選手権などのポイントを得るため、前半戦に一線級選手を投入してくる。第4戦になると消化試合とはいかないまでも、ビッグネームはそういない。しかし、初戦となれば話しは別だ。そこで脇本は金メダルを獲ったのだから、チリ大会Vがフロックでなかったことを証明できたとも言える。

今シーズン第5戦(ケンブリッジ)では新田祐大が自身初となるW杯銅メダル。チームスプリント(雨谷一樹・新田・深谷知広)も銀メダルを。男子だけではなく、第3戦(ベルリン)では小林優香も初の銅メダルに輝く。そして、まさにこの原稿を書いている時の第6戦(香港)では河端と太田りゆも銀メダルの快挙となった。


ここまでの快進撃が続くのは2016年10月にヘッドコーチに就任した“メダル請負人”の異名を持つブノワ・ベトゥの力によるところが大きい。しかし、就任当初、ナショナルチームのメンバーは半信半疑だったそうだ。専門的になってしまうので詳しいことは割愛するが、技術的な部分よりもメンタル面を重視した指導ということらしい。過去、日本が五輪でメダルを獲得したのは1984年ロス五輪の坂本勉(スプリント・銅)、1996年アトランタ五輪の十文字貴信(1kmTT・銅)、2004年アテネ五輪の長塚智広・伏見俊昭・井上昌己(チームスプリント・銀)、2008年北京の永井清史(ケイリン・銅)の4大会だけだ。失礼な言い方だが、ロス五輪は東側共産圏諸国が不参加。アトランタ五輪の十文字は金メダルが最右翼のシェーン・ケリー(オーストラリア)がアクシデントに見舞われ棄権。アテネと北京の場合、両大会ともヘッドコーチは外国人、アテネ五輪はオーストラリア人のゲーリー・ウエスト、北京五輪はフランス人のフレデリック・マニェだった。
以前にもここで外国人コーチのことについて書いたが、自転車の場合はここまで成果が出るとは思っていなかった。正直、出場国枠を掴むのに精一杯なのではないかというところ。しかしながら現在は出場国枠どころか、メダルの可能性、それもどの色のメダルが獲れるかという話題になっている。あまりにもポジティブ過ぎる考えかも知れないが、ここ最近の成績を見れば、現実味を帯びている話しである。ただ、残念なのは相も変わらずメディアの扱いが小さいことだ。
脇本をはじめ、新田などは2019年も競輪競走の参加は昨年以上に少なくなると聞いている。競輪ファンからしてみれば、脇本の先行、新田の捲りを競輪場でも観たいに決まっている。売り上げ面で他の公営競技から遅れを取っている今、彼らの走りは売り上げにも大きく左右してくる。だからこそ競輪業界がすべきことは、もっと分かりやすく、しつこいくらいに脇本や新田らのナショナルチームの選手と五輪との関係性をアピールすることではないだろうか。競輪ファンの支持もあってこそ、2020年東京五輪も盛り上がるはずである。
Recommend
New Article|コラム
2024/04/25
2024/04/24
2024/04/21
Recommend
NEW
2024/04/25
NEW
2024/04/25
NEW
2024/04/25
NEW
2024/04/23
NEW
2024/04/23